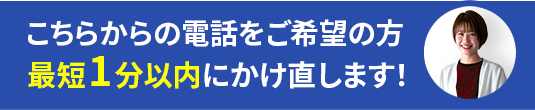福島市の防災への取り組み・災害対策まとめ!市民が参加できるイベントも紹介
この記事では、福島市が取り組む防災対策や災害への備えについて詳しくご紹介します。
地震や風水害、雪害など幅広い災害リスクに対応する体制の整備に加え、企業や大学との連携、市民参加型のイベントなども実施されています。
住民の安全を守るための仕組みや日常からできる備えについても解説していますので、防災意識を高めたい方にも役立つ内容です。福島市の現状を知るきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
福島市の防災に対する取り組みの全体像!各種災害に対応
福島市では、地震や風水害、火山災害といったさまざまなリスクに備え、市全体での防災体制を強化しています。災害時における住民の安全確保と地域全体のスピーディな対応を目的と、福島市地域防災計画が策定されており、各機関や地域住民が一体となって行動できる仕組みづくりが進められています。
災害はいつどこで発生するか分からないからこそ、準備と明確な方針が欠かせません。ここでは、福島市における防災の全体像と、それを支える独自の計画について詳しく見ていきましょう。災害別の対策については次の項目からご紹介していきます。
福島市地域防災計画の概要
福島市では、市の特性や過去の災害経験を踏まえて、独自の地域防災計画を策定しています。この計画は、災害発生時における行政機関や住民の役割、応急対策、復旧体制までしっかり網羅しており、まさに防災の根幹を成す存在です。
内容は定期的に見直されており、社会情勢や災害リスクの変化に応じて柔軟に対応できる体制が整備されています。行政だけでなく、地域の企業や学校とも連携することで、実効性の高い防災ネットワークが構築されている点も大きな特徴です。
自助・共助・公助の連携強化
福島市の防災体制において重要視されているのが、自助・共助・公助の三位一体の考え方です。
個人や家庭での備え(自助)だけではなく、地域内での助け合い(共助)、そして行政による支援(公助)を有機的に結びつけることで、より強靭な防災力を育てようとする姿勢が貫かれています。
地域ごとの防災会や自主防災組織の活動が活発で、住民が主体的に訓練や勉強会に参加するなど、日常から防災への意識を高める環境が整っています。
防災拠点と運営体制の整備
災害が発生したときにスムーズな対応を実現するため、福島市では市内各所に防災拠点を設けています。
- 市内の小・中学校
- 福島市の施設
- 道の駅
- 指定避難所
これらの拠点は避難所の運営や物資供給の中核となる場所であり、役割分担や運営マニュアルが整備。また、災害対策本部の機能強化や、情報共有のためのICT活用も進んでおり、状況に応じた柔軟な対応が可能な体制づくりが進められています。
以下、災害別に福島市での防災に関する取り組みを見ていきましょう。
福島市の防災に対する取り組み!「地震・津波」対策編
福島市では、いつ起きてもおかしくない地震や津波への備えを、地域特性や過去の災害データに基づいて整備しています。ここでは、福島市がどのように地震・津波リスクへ対応しているのか、具体的な対策を見ていきます。
想定震源と被害シナリオの明確化
福島盆地西縁断層帯の地震(想定マグニチュード7.1、震度最大7)を中心に、市では冬の夕方を想定した震災シナリオが設定されています。
この想定では、全市的な建物の倒壊や、鉄道・高架橋など交通インフラの損壊、帰宅困難者の発生などが想定されており、行政・住民両方が対応できるよう設計されています。
建物とインフラの耐震性能向上
市内の公共施設や避難施設では耐震診断が義務づけられ、緊急性に応じて順次補強・改修が進められています。
住宅や民間建築物についても、耐震化の啓発や診断支援を通じて耐震対策が促進されており、福島市独自の「耐震改修促進計画」に基づいて地震に強いまちづくりを推進しています。
一次・二次被害への備え
液状化やがけ崩れ、ブロック塀の倒壊、家具の転倒・落下物対策など、地震による二次被害にも着目し、それぞれのリスクに応じた細かい対策が設定されています。
特に危険な塀の調査や改修指導を通じて、避難や救援活動の妨げにならないよう環境整備が進められています。
緊急輸送路と避難拠点の整備
災害発生時に迅速な対応ができるよう、東北自動車道や主要国道などを緊急輸送路として指定し、市内各拠点と連携するネットワークが確立されています。
災害対策本部や病院、広域避難場所を接続する輸送路を多層的に整備し、救援物資や要員の移動が滞らない体制を構築しています。
福島市の防災に対する取り組み!「水害・土砂」対策編
都市部と山間部に分かれる福島市では、台風や大雨に伴う洪水や地滑りのリスクに対応するため、水害や土砂災害への備えも整えています。
具体的な内容を順番に見ていきましょう。
水害への包括的対策
福島市は、阿武隈川をはじめとする河川の治水整備を進め、都市域の浸水被害を抑える取り組みが進められています。
洪水ハザードマップの整備と周知に力を入れ、特に要配慮者施設(社会福祉施設、学校、医療施設など)への情報伝達手段を確保するなど、地域の安全を確実に守る仕組みが整備。
また、下水道ネットワークの整備や維持管理を促進し、大雨時の排水能力強化を図っており、内水氾濫への備えも強化されています。
土砂災害への予防と警戒体制
山間部は、地すべりや急傾斜地崩壊、土石流といった土砂災害の危険箇所が多く存在します。市と県が連携して土砂災害警戒区域を指定し、地形や降水条件に基づいた調査を定期的に実施。
危険箇所の周知や住民向け広報活動を通じて、避難行動への備えを促しています。特に危険度の高い区域では、避難情報の整備や避難訓練の計画が地域防災計画に明記されており、地域全体で警戒体制を維持しています。
警戒区域の指定と避難行動計画
土砂災害防止法に基づいて、県が土砂災害警戒区域および特別警戒区域を指定し、その範囲に応じて市町村が避難指示・避難誘導・訓練実施の体制を地域防災計画に盛り込んでいます。
要配慮者施設についても、避難体制が担保されるよう情報連携の仕組みが整備されています。
砂防・斜面対策の強化
土石流危険渓流や地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊の恐れがある地域に対しては、砂防堰堤や地下排水設備、法面工による斜面保全工事が進められています。
さらに、森林整備や治山事業を通じて山地の安定化が進められ、長期的な観点から土砂流出を防ぐ取り組みが継続されています。
情報発信と地域教育の推進
福島市では洪水や土砂災害に関するハザードマップの配布や、一般向けの啓発活動を積極的に実施しています。さらに、毎年の啓発月間にあわせた広報活動や住民参加型の講習を通じて、防災意識の向上を図っています。
こうした情報発信は、災害時の迅速な避難行動につながる大きな柱と言えるでしょう。
福島市の防災に対する取り組み!「雪害・冬季」対策編
福島市では、厳しい冬季の雪害と寒波に備え、交通の確保から地域の助け合いまで、多方面で防災体制を構築しています。
降雪期特有の課題を想定しながら、行政と住民が連携して雪害に対応できる仕組みを整備している点が福島市ならではの特徴です。
道路除雪体制と交通確保の設計
福島市地域防災計画に基づき、冬季は主要幹線道路を中心に計画的な除雪を実施する「道路除雪計画」が定められています。重要な緊急輸送路は第1種路線と指定され、優先的に除雪が実施される仕組みです。
福島市は、直営班と委託業者の協力の下で除雪を実施し、一定量の積雪(目安として平地で12時間に25 cm)で除雪対策本部を設置。市内の交通網を維持しつつ、市民の移動の安全を確保しています。
気象情報と市民への発信・協力体制
気象情報をリアルタイムで収集し、防災メールやLINE、X(旧Twitter)、防災アプリを通じて迅速に市民へ通知。降雪が予報された場合や注意報・警報が出たときは、除雪支援の呼びかけや行動指針を提示し、市民や地域団体が自主的に除雪へ参加できる環境づくりを進めています。
小型除雪機の貸出や資器材貸出支援を行うアダプト制度も導入されています。
地域協力の除雪支援
除雪を地域ぐるみで支えるため、福島市は地域団体や町内会と連携し、住民主体の除雪活動を助成・支援します。
アダプト制度では、歩道等の除雪区画を行政とともに設定し、小型除雪機械の導入補助やボランティア保険への加入支援などを通じて、住民が過度な負担なく助け合える仕組みを整備しています。
避難路・避難場所と備蓄体制の確保
積雪や凍結により避難経路や避難所のアクセスが困難になる冬期を想定し、福島市は避難路の確保や暖房資機材の整備にも配慮しています。非常時でも避難所が機能するよう暖房器具、防寒具、雪かき具などを備蓄。
また、停電時の電源確保のため、ガス式発電機の設置なども視野に入れ長期避難生活への準備も見込んでいます。
安全性への配慮と要支援者への対応
屋根雪の荷重による住宅被害や雪下ろし中の事故、防火水利の除雪など、安全確保も重要な柱です。
地域の助け合いによる屋根の雪処理や、高齢者・要援護者の孤立防止に向けた情報管理・支援体制の整備によって、雪の重みで生じるリスクに備えています。
福島市の防災に対する取り組み〜企業・大学・団体との連携について〜
福島市では、防災体制をより強くするため、企業や大学、専門団体との連携を積極的に進めています。ここでは、地域とどのような取り組みが進められているか紹介します。
企業と学生団体の教育協働プログラム
福島大学の学生団体「災害ボランティアセンター」と損害保険ジャパン(福島支店)が連携し、「防災リュックを考えよう」という体験型教材を共同開発しました。
ゲーム感覚で自分に必要な防災グッズを選ぶワークショップ形式の講座で、子どもから大人まで楽しみながら防災意識を高める仕組みを全国へ展開しています。
災害協定による人的支援ネットワーク
福島市は、他の自治体や地元の看護専門学校3校と「災害時応援協定」を締結しました。
- 一般財団法人大原記念財団 大原看護専門学校
- 公益社団法人福島明星厚生学院 福島看護専門学校
- 学校法人東稜学園 福島東稜高等学校
要支援者を受け入れる避難所に向け、学生ボランティアによる支援体制を整備し、災害時にも安心して避難できる環境を確保しています。
※参照元:福島市
消防団への支援を通じた地域参加の促進
消防庁が推進する「女性・若者等の消防団加入促進支援事業」を活用し、地元企業や大学等との協働により、地域の防災中核である消防団への参加を呼びかけています。
また、協力企業には特典を提供し、地域全体で消防団を支える風土をつくっています。
福島市が開催する防災イベント【ふくしま防災体験フェア】
福島市では、市民一人ひとりが防災に関心をもち、行動へとつなげるきっかけとして「ふくしま防災体験フェア」が開催されています。このイベントは、地震や土砂災害の模擬体験を通じて、災害時に必要な知識や備えを体感的に学べる貴重な機会です。
子どもから大人まで幅広い世代が参加できるよう工夫されており、街中で気軽に防災を学べる体験型イベントとして注目を集めています。消防本部の協力のもとで行われる働く車の展示や記念撮影コーナーなども人気の一つで、楽しく学ぶことを目的とした市民参加型の取り組みとなっています。
楽しみながら防災を身近に感じられるため、災害に強いまちづくりの一環として今後も期待されるイベントです。
福島市の防災への取り組みは万全!市民も各自で備えを!
本記事では、福島市が進める防災対策の全体像と、市民が主体的に関われる取り組みについて紹介しました。
ここまで見てきたように、福島市ではさまざまな災害に備えた施策が充実しており、地域ぐるみで防災力を高めています。この機会にぜひ、ご家庭の備えも見直してみましょう。
福島市内の水漏れ修理やトイレの詰まりは、マルキンクリーンにお任せください。
- 3,300円〜対応
- 最短30分で現場に駆けつける地域密着型サービス
- 24時間365日受付
- 出張・見積もり無料
今ならWEB限定3,000円割引も実施中ですので、まずはお気軽にご相談ください!
宮城・福島・山形エリア対応
実績豊富なプロが即対応!
水道局指定工事店
24時間365日対応

\最短30分でスピード解決/
- 福島市の防災計画にはどんな内容が含まれていますか?
-
福島市地域防災計画には、地震や水害、雪害など自然災害への対応方針や、災害時に行政や市民が果たす役割、避難所の運営方法、支援物資の流通体制などが定められています。状況に応じて定期的に見直され、最新のリスクに対応できるよう整備されています。
- 福島市では災害に備えてどのような避難体制が整っていますか?
-
福島市では、市内の小・中学校や市施設、道の駅などを避難拠点として指定し、災害発生時に速やかに避難できる体制を整えています。避難所には生活必需品や防寒具も備蓄されており、要支援者への配慮も含めたマニュアルが整備されています。
- 防災イベントに参加したいのですが、申し込みは必要ですか?
-
申し込み不要で自由に参加できる形式がほとんどです。たとえば「ふくしま防災体験フェア」は年に一度、市中心部で開催され地震体験や働く車とのふれあいなど、気軽に防災を学べる内容が用意されています。開催情報は市の公式サイトで随時確認できます。
24時間365日対応! 出張・お見積もり無料! ※深夜帯(22時~5時)は出張費・見積費をいただく場合があります。
今ならWEB限定で3,000円割引中!
0120-365-891