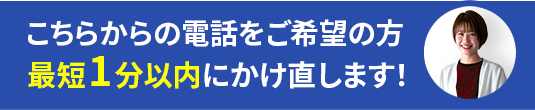水質検査11項目の義務があるのはどんなとき?対象建物・業種・具体事例を徹底解説
この記事では、水質検査11項目が法律で義務付けられているケース、事業内容・施設別に必要となる水質検査(項目数)について徹底解説していきます。
「自分の事業・管理施設で必要な検査は11項目であってる?」
「水質検査11項目は回避できない義務?放置したときの罰則規定は?」
「最低限検査にかかる費用の目安は?」
といった疑問をお持ちの方も必見です。
水質検査はビルや飲食店、宿泊施設など多くの建物・施設で義務化されています。法律で定められた基準を満たすため、定期的な検査の実施が求められており、怠ると罰則の対象に。
該当する事業・施設の一覧はもちろん、記事後半では、正しい検査頻度や、16項目・51項目などと間違えられやすいケースもご紹介。さらには、検査費用を少しでも抑えるコツまで丁寧に解説しますので、最低限の出費で抑えたい事業者や施設の管理者の方はぜひ最後までご覧ください。
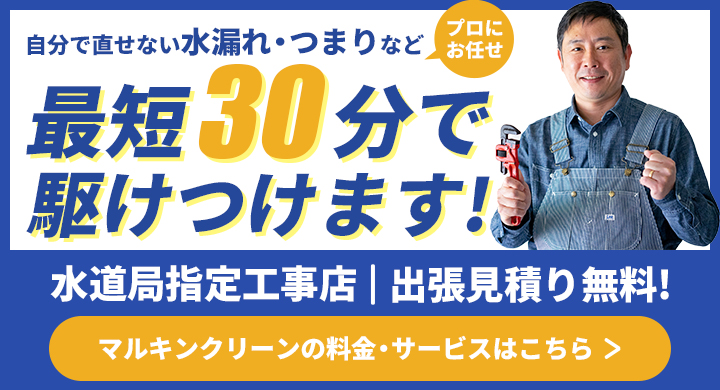
水質検査11項目が義務のケースとは?対象の建物・施設まとめ
「ビル管理法」と呼ばれると、大型ビルだけが対象と思われがちですが、実際は飲料水を供給する多くの建物が検査義務の範囲に含まれます。法律上は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が正式名称であり、オフィスや商業施設に限らず、幅広い事業施設が対象とされています。
具体的には、延べ床面積が3,000㎡を超える特定建築物が主な対象です。
- 百貨店
- ショッピングモールなどの大型店舗
- 映画館やコンサートホールなどの興行場
- 事務所
- 学校
- 図書館
- ホテル
- 旅館
- 結婚式場
- イベントホール
- 美術館
- 博物館
- 遊技場
これらの施設では、不特定多数の人が日常的に水を利用するため、飲料水の安全確保が強く求められています。そのため、定期的に水質検査を実施し、基準を満たしているか確認しなければいけません。
水質検査11項目はどんな業種で実施?義務とされる理由や違反・事故事例も
水質検査11項目は、水道水や井戸水を利用する幅広い業種で義務化されています。食中毒や感染症の原因となる細菌や有害物質を未然に防ぎ、利用者の安全を守るために必要不可欠な取り組みです。
実際、過去に水質検査を怠ったことで行政指導や営業停止に至った事例も報告されています。ここでは、具体的にどのような業種で水質検査が必要とされているのか見ていきましょう。
飲食/サービス業/宿泊施設
飲食店やホテル、旅館といった業種では、日常的に提供される水の安全性が直接的に利用者の健康へ影響します。そのため、営業許可を得る際や定期的な検査として水質検査が必要です。
実際に、飲食店での水の管理不備により大腸菌が検出され、営業停止処分となった事例も。こうした事態を防ぐためにも、検査を欠かさず実施しなければいけません。
プール/温泉施設
プールや温泉は不特定多数の人が利用するため、水質管理を徹底しなければいけません。残留塩素濃度や一般細菌の基準を満たさなければ、レジオネラ属菌による感染症など重大な健康被害を引き起こす恐れがあります。
温泉施設で水質管理を怠った結果、多数の入浴客が感染症を発症し、施設が長期間営業停止となる事態にも発展しかねません。このようなリスクを避けるためにも、定期的な水質検査が必要です。
食品工場/加工工場
食品製造工場や加工工場では、水は原材料や製造工程に広く使われます。水質が基準を満たしていなければ製品の安全性に直結し、リコールや行政処分につながる可能性があります。
実際に、井戸水を使用していた食品工場で大腸菌群が検出され、大規模な商品の回収に発展した事例も。事業継続に重大な影響を及ぼすことから、食品関連業種にとって水質検査は必須です。
水質検査11項目が義務のケース2つ【51・16・10項目などとの違いとは】
水質検査には51項目や16項目といった大規模な調査から、省略が認められる11項目、さらに自主的に実施する10項目まで複数の種類があります。法律で義務付けられたものと、任意で実施する検査があるため、自分の施設や事業にどの検査が必要かを正しく理解しておきましょう。
ここでは、「11項目」が義務となるケースと、51・16・10項目との違いについて整理して解説します。
基本の水質調査から一部省略可能なケース
水質検査の基本は、水道法や水質基準省令に基づく「51項目」の水質基準検査です。ただし、すべての施設が常に51項目実施するわけではなく、対象や条件によって「16項目」や「11項目」へ省略できる場合があります。
法令や条例に基づかない自主的な調査であれば「10項目」の検査でも構いませんが、営業許可や行政向けの対応には使えないため注意しましょう。
使用する水が直結の水道でないケース
建物で利用する水が水道局から直接供給される「直結給水方式」であれば、通常は水質検査を求められません。しかし、貯水槽や井戸水を使用している場合、11項目の検査が義務化されるケースが多くなります。
- 貯水槽経由(タンク水)の場合
- 井戸水の場合
2つのケースについて見ていきましょう。
貯水槽経由(タンク水)の場合
ビルや商業施設、宿泊施設などでは貯水槽を経由して水を利用するのが一般的です。この場合、営業許可や衛生管理のために水質検査11項目を毎年実施しなければなりません。
さらに、貯水槽の清掃や点検も法律で義務付けられており、水質検査とあわせて衛生管理も必須です。
井戸水の場合の2回目以降(定期検査)
井戸水を利用する場合、新規開業時にはより多くの検査が必要です(26項目や51項目など)。
これは、井戸水が水質の変動を受けやすいためであり、定期的に基準を満たしているかの確認が必須となります。
水質検査11項目が義務のケースでは何を調べる?基準値もチェック!
水質検査11項目は、飲料水の安全を確認するために最低限義務付けられている検査内容です。検査の目的は、病原菌や有害物質の混入を防ぎ、水質の異常を早期に把握することにあります。
以下の表で各項目の内容と基準値を整理しました。
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlあたり100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 合計10mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素:TOC) | 3mg/L以下 |
| pH値 | pH5.8以上pH8.6以下 |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 味 | 異常でないこと |
ここから、それぞれの項目について具体的に見ていきましょう。
一般細菌・大腸菌
一般細菌は水中に広く存在し、基準を超えると衛生状態の悪化が疑われます。特に大腸菌は人や動物由来の汚染を示す重要な指標で、飲料水からは検出されてはいけません。
安全な水の供給に欠かせない基本の検査項目です。
味・臭気・色度・濁度
水の見た目や匂い、味に異常がないか確認する検査です。配管の劣化や有機物の混入によって味や臭気が変化することがあり、色度や濁度の上昇は水の透明性低下を意味します。
いずれも基準値を超えると飲料水としての安全性が損なわれるため、定期的な確認が必要です。
pH値
水の酸性・アルカリ性を示す数値で、設備の腐食や水質変化を見極める重要な指標です。基準値は5.8~8.6の範囲内で、この値を外れると水質トラブルや健康被害のリスクが高まります。
その他
塩化物イオンや有機物(TOC)、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素なども重要な検査項目です。肥料や生活排水、工場排水などから水に入り込み、過剰になると健康被害や水質汚濁の原因となります。
いずれも基準を超えないように管理することが、安全な水を提供する上で欠かせません。
水質検査11項目が義務の場合の実施方法2つ!自社でも可能?
水質検査11項目は、飲料水の安全を確保するために義務付けられている検査です。実施方法は大きく分けて「水道業者など専門機関に依頼する方法」と「水質検査キットを使って自社で行う方法」があります。
どちらを選ぶにしても、基準を満たす確実な検査を実施するのが一番大切です。
水道業者に依頼する
最も一般的で安心なのは、水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録の水質検査機関や水道業者に依頼する方法です。検査機関が適切に採水し、専門の分析機器で測定するため、精度や信頼性が高い点が特徴です。
費用は地域や業者によって異なり、相場は7,000円〜10,000円前後。納期は1週間程度が目安となります。
依頼することで報告書も正式に発行されるため、保健所への提出や行政対応にもそのまま利用できます。
水質検査キットで自社検査する
市販されている水質検査キットを利用すれば、自社で手軽に検査することも可能です。自分で採水して郵送する簡易タイプもあり、日常的な水質チェックには有効と言えます。
ただし、検査精度や法的効力の点で業者依頼に劣り、営業許可の申請や行政報告には利用できないケースも。そのため、確実な結果と正式な証明を求める場合は、水道業者や登録検査機関に依頼するのが最も安心で手間もかからない方法です。
宮城・福島・山形エリア対応
実績豊富なプロが即対応!
水道局指定工事店
24時間365日対応

\信頼と実績のサービス/
水質検査11項目の義務を満たす上での注意点3つ
水質検査11項目は、飲料水の安全を守るために法律で定められた検査です。しかし、正しい方法で実施しなければ、罰則や営業停止など思わぬリスクにつながります。
ここでは、水質検査11項目を実施する際に必ず押さえておきたい注意点を整理しました。
頻度を守らない・検査を怠ると罰金
水質検査は原則として年1回以上の実施が義務付けられています。検査を怠る、実施間隔を守らないと、行政指導や30万円以下の罰金を受ける可能性があります。利用者の安全を確保するだけでなく、事業継続のためにも必ず定期的に実施しなければいけません。
ビル管理法に該当している場合は資格保有者のみ検査可能
延べ床面積3,000㎡以上の建築物など「特定建築物」に該当する施設では、ビル管理法に基づき水質検査を実施する義務があります。検査はビル管理士などの資格をもつ専門業者に依頼しなければなりません。
資格をもたない業者や自社での簡易検査では、法的要件を満たせないため注意しましょう。
検査結果も5年間保有の義務がある
水質検査の結果は、ただ提出するだけで終わりではありません。検査後の報告書は法律により5年間の保管が義務付けられています。
記録をきちんと残しておかないと行政から指摘を受ける可能性があるため、書類の管理も徹底しましょう。万が一のトラブル発生時、検査記録が正しく残っていれば適切に対応できるため安心です。
水質検査11項目は義務!検査は水道業者に依頼するのが確実!
本記事では、水質検査11項目の対象となる建物、実施方法や注意点について詳しく解説しました。
水質検査は法律で定められており、怠れば罰則や信頼低下につながるため、管理者にとって重要な業務です。安全で清潔な水を維持するには、自社対応よりも専門業者に依頼するのが安心で確実な方法と言えます。
マルキンクリーンでは、ビルや飲食店、宿泊施設、工場など幅広い施設の水質検査に対応しており、見積もりは無料です。水質検査の不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
宮城・福島・山形エリア対応
実績豊富なプロが即対応!
水道局指定工事店
24時間365日対応

\信頼と実績のサービス/
- 水質検査11項目は義務ですか?
-
井戸水や貯水槽使用水を利用する施設、またはビル管理法の対象となる特定建築物では水質検査11項目が義務です。直結給水方式の水道を利用している場合は不要ですが、自治体や業種によって追加項目が求められる場合があります。
- 水質検査は11項目だけで十分ですか?
-
施設や利用する水の種類によって必要な項目数は異なります。新規で井戸水を使う場合は26〜51項目の検査が求められ、その後の定期検査として11項目が義務になります。商業施設や不特定多数が利用する建物では16項目や51項目が必要なケースもあるため、必ず管轄の保健所に確認しましょう。
- 検査の費用や依頼先はどこを選べば良いですか?
-
費用の相場は7,000円〜10,000円程度で、検査機関によって異なります。営業許可申請や行政報告に使用するには、水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録の水質検査機関や水道業者に依頼する必要があります。市販の簡易キットでは法的効力がないため、正式な検査は必ず専門業者に依頼してください。
24時間365日対応! 出張・お見積もり無料! ※深夜帯(22時~5時)は出張費・見積費をいただく場合があります。
今ならWEB限定で3,000円割引中!
0120-365-891