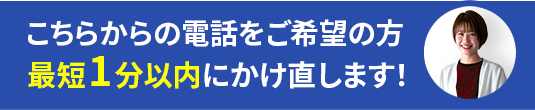グリストラップ清掃は誰がやる?事業者側と専門業者の作業分担とは【従業員OKの範囲も】
この記事では、業務用厨房に設置されているグリストラップの清掃を、誰がやるべきなのかについて解説していきます。
グリストラップの清掃は、つまりの予防のほか、衛生管理や法令遵守においても重要な業務です。ただし、業者への依頼基準を理解しておかないと、勧告や罰則の対象になる可能性もあります。
店舗側でできる作業から業者が必要な作業、自身で行うリスクや業者に依頼するメリットまでご紹介。飲食店やホテルなどの事業者や、厨房責任者の方はぜひチェックしてみてください。
グリストラップの清掃は「何か起きる前」が大切です!
宮城・福島・山形エリア対応
実績豊富なプロが即対応!
水道局指定工事店
24時間365日対応

\事業に悪影響が出る前に/
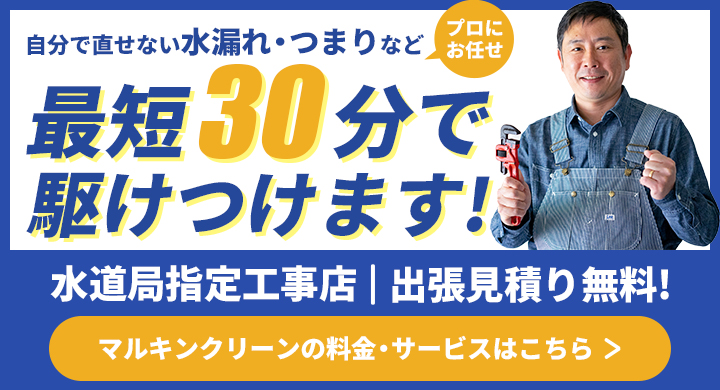
グリストラップ清掃は誰がやる?業者依頼は必須?
グリストラップの清掃は、厨房の衛生を保つうえで欠かせない業務です。しかし、「誰が対応すべきなのか」「業者に頼まないといけないのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、一部の作業は店舗スタッフでも対応可能ですが、法的に業者依頼が必要な作業も存在します。
ここでは、その境界について分かりやすく整理します。
グリストラップの清掃に必要資格はない
まず、グリストラップの清掃自体には特別な資格は必要ありません。
たとえば、バスケット(ごみ受け)のごみを取り除いたり、表面に浮いた油をすくい取ったりする作業は、店舗従業員でも日常的に行える範囲の清掃です。
実際、衛生管理の観点からも、軽度な清掃は営業終了後や営業前にこまめに行うのが推奨されており、これを継続することで業者依頼の頻度も抑えられます。
認可業者への依頼が必要な作業
グリストラップ内部にたまった油脂や汚泥(スカム・スラッジ)を取り除いて処分する作業には注意が必要です。この汚泥は「産業廃棄物(汚泥)」に分類されるため、回収・運搬・処分を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼する必要があります。
無許可業者や自社で不適切に処理した場合、違法行為となる可能性があります。
また、大型施設や屋外型グリストラップの場合、専用の吸引車や高圧洗浄機が必要になるケースも多く、専門業者でなければ対応が難しいのが実情です。
汚泥処理で規則に違反した際の罰則
産業廃棄物に該当するグリストラップの汚泥を法律に反して処理した場合には、罰則が科せられる可能性があります。
具体的には、廃棄物処理法違反により以下のような罰則があります。
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)
- 営業停止や業務改善命令の対象
また、場合によっては施設の営業に深刻な影響を及ぼすこともあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、回収・処理が必要な作業は必ず認可を受けた専門業者に依頼することが基本です。
グリストラップ清掃を店舗従業員がやる場合の作業可能項目
グリストラップは通常、以下3つの槽(第1槽〜第3槽)で構成されており、それぞれ役割が異なります。
- 第1槽(バスケット)のごみを除去する
- 第2槽の汚泥(油脂・沈殿物)を取り出す
- 第3槽(トラップ管)を清掃する
このうち、日常的なメンテナンスとして従業員が対応可能な範囲も多く、こまめな清掃を心がけると、悪臭や詰まりの予防、清掃業者への依頼頻度削減にもつながります。
ここでは、店舗スタッフでも対応しやすい作業を各槽ごとに紹介します。
第1槽(バスケット)のごみを除去する
第1槽は、シンクなどから流れてきた食材カスや大きなごみを受け止めるバスケット(ごみ受け)が設置されている場所です。
このバスケット内には、料理中に出た野菜くず・米粒・骨・残飯などが溜まります。放置すると悪臭や害虫発生の原因になるため、毎日の営業後に取り除くのが理想的です。
作業手順はシンプルで、ゴム手袋とトングなどを使用し、バスケットを取り外して中身を廃棄し、軽く水洗いして元に戻すだけ。
比較的負担の少ない作業のため、日常清掃のルーティンに組み込むことが推奨されます。
第2槽の汚泥(油脂・沈殿物)を取り出す
第2槽は、水面に浮いた油脂や、底に沈んだ汚泥を分離して溜めておく槽です。ここでは、食用油やラードなどの油脂成分が浮遊し、調理排水に含まれる微小なゴミや沈殿物が底に溜まっていきます。
この汚れは時間が経つほどこびり付き、悪臭やつまりの原因になるため、週1〜2回程度を目安に定期的な清掃が必要です。
作業には、以下の工程などが含まれます。
- 油脂をおたまやバキュームポンプで取り除く
- 汚泥をスコップや柄の長いスプーンなどで掻き出す
- 槽の内壁をブラシで軽くこすって洗い流す
多少の手間はかかりますが、従業員でも十分対応可能な範囲です。
第3槽(トラップ管)を清掃する
第3槽は、排水の最終段階に位置し、排水管へ流す直前に異物をせき止める役割を持っています。この槽にはトラップ管(U字状の配管)が設けられており、異臭や害虫が排水管から逆流するのを防ぐ仕組みです。
ここには比較的小さな異物や油膜がたまりやすく、目視での確認が難しい場合もあります。
週1回程度、蓋を開けて棒状のブラシや洗浄剤を使って内部を清掃すると、詰まりやニオイを防げます。
注意点として、無理に分解を行うと配管を傷つける恐れがあるため、あくまで届く範囲での清掃にとどめ、異常があれば業者に相談するのが安全です。
グリストラップ清掃を店舗の誰かがやるリスク
グリストラップの清掃は、一定の範囲であれば従業員でも対応可能ですが、業務の一環として店舗スタッフに任せることにはいくつかのリスクが伴います。とくに人手不足や清掃への理解不足がある現場では、かえって衛生環境を悪化させてしまうことも少なくありません。
ここでは、店舗内で清掃を完結させようとする際に起こりうる4つの代表的なリスクをご紹介します。
作業負担が大きい
グリストラップ清掃は、悪臭・汚泥・油脂に直接触れる重労働です。限られた時間の中でこのような作業を日常業務に加えることは、従業員にとって大きな負担となりがちです。
特に暑い季節や繁忙期は、体力的にも精神的にも負荷がかかり、作業そのものが雑になったり、手を抜かれたりする恐れもあります。また、負担の大きさから清掃を敬遠するスタッフが増えると、作業を任される人が偏るという新たな問題も生じます。
衛生状態を悪化させるおそれがある
不慣れなスタッフが清掃を行うと、清掃の仕方や頻度が不十分になりがちです。その結果、グリストラップ内に油脂や汚泥が蓄積し、以下のような問題が起きる可能性が高まります。
- 排水管の詰まり
- 悪臭の発生
- ゴキブリやコバエなどの害虫発生
また、人員が不足していたり、清掃担当が曖昧になっていたりすると、清掃スケジュール自体が崩れてしまい、結果として衛生状態が大きく悪化するリスクにもつながります。
清掃業務が店舗責任者に集中しかねない
実際の現場では、「誰もやりたがらない」「割り当てづらい」という理由から、グリストラップの清掃が店長や責任者の仕事になってしまうケースも少なくありません。
その結果、責任者が日常業務に加えて重たい清掃作業まで担うことになり、本来優先すべき業務に集中できない、疲労が蓄積する、人員配置に支障が出るといった運営上の問題が発生する場合があります。
また、従業員に無理に押しつければ職場環境が悪化し、離職の引き金になるケースもあるため、慎重な対応が必要です。
健康被害のリスクがある
グリストラップ内には、腐敗した油脂やヘドロ、細菌類が大量に蓄積しています。これらに長時間・無防備に接触すると、従業員の健康被害(嘔吐、めまい、皮膚炎、感染症など)につながる可能性もあります。
とくに防護具を十分に装着せずに作業を行うと、飛沫や臭気による体調不良やアレルギー反応を引き起こす危険性が高まります。こうしたリスクを避けるためにも、従業員が対応する範囲には限界があることを理解し、必要に応じて専門業者への依頼を検討しましょう。
グリストラップ清掃は専門業者への依頼が基本!メリット4選
グリストラップの清掃は、一部は店舗スタッフでも対応可能ですが、根本的な解決や法令順守、安全性を考えると、専門業者への依頼が基本です。
専門業者に任せることで得られる4つの主なメリットは以下の通りです。
- スタッフの負担やリスクを減らせる
- 専門技術で徹底的に洗浄できる
- 地面に深く埋設された設備でも心配不要
- 改善勧告や営業停止処分などのリスクを回避
とくに飲食店や施設では、衛生管理の不備が営業リスクに直結するため、定期的なプロの介入が欠かせません。
ここでは、それぞれのメリットについて紹介します。
スタッフの負担やリスクを減らせる
グリストラップ清掃は、悪臭・汚泥・油脂の処理を伴う身体的にも精神的にも負担の大きい作業です。清掃を社内で完結させようとすると、スタッフのモチベーション低下や、衛生意識のばらつきにつながるおそれがあります。
一方、専門業者に依頼すれば、こうした作業を従業員に強いる必要がなくなり、本来の接客や調理業務に集中させられます。人手不足や新人スタッフが多い現場でも、清掃体制を安定させられるのは大きなメリットです。
専門技術で徹底的に洗浄できる
専門業者は、高圧洗浄機や吸引車、産業用バキュームなどの専用機材を使って、店舗スタッフでは手の届かない部分までしっかり清掃してくれます。
特に第2槽や第3槽の奥、排水管の入口付近などは、見た目では分からない油脂や汚泥が大量に付着している場合が多く、蓄積すると悪臭や排水不良の原因になります。
業者に任せることで、定期的に「内部から徹底洗浄」でき、厨房の衛生レベルを高く保ちやすくなります。
地面に深く埋設された設備でも心配不要
屋外に設置されている大型のグリストラップや、地面に埋設されたタイプは、開口部が狭く深さもあるため、とても危険を伴う作業になります。実際に過去には、清掃中に中へ転落してしまい、重大な事故につながったケースも報告されています。
2023年8月14日、広島市安佐南区の市立保育園で、57歳の女性調理員がグリストラップの清掃中に死亡する事故が発生しました。
引用元:千葉県水まわり解決センター
こうした場所での清掃は、適切な知識と安全対策を備えたプロに任せるのが鉄則です。
専門業者であれば、点検口の確保から安全柵の設置、落下防止措置、2人1組の作業体制など、労働安全を前提とした作業を行うため、事故のリスクを大幅に軽減できます。
改善勧告や営業停止処分などのリスクを回避
飲食店や食品工場などでは、保健所による衛生チェックが定期的に行われます。その際、グリストラップが不衛生だったり、悪臭・害虫・詰まりが確認されたりした場合、改善勧告や営業停止命令を受けるリスクがあります。
とくにグリストラップは「外からは見えにくい場所」だからこそ、見落としがちな衛生リスクの温床になりがちです。
専門業者に定期清掃を依頼しておけば、施設基準や衛生管理項目にも沿った対応が可能となり、こうしたリスクを事前に防げます。
グリストラップ清掃を誰がやるかは原則専門業者!自力でできる範囲は相談を!
グリストラップの清掃は、自分でできる作業もありますが、できるだけプロの業者を頼りましょう。店舗従業員の負担を軽減でき、徹底的な洗浄でより長期的な維持が見込めます。
スタッフの怪我や健康被害に加え、つまりなどの経営リスクもあるので、専門業者に任せておけばその点安心です。
排水の流れが悪くなってきた場合や、完全につまってしまった場合なども、幅広い水道トラブルに対応可能な『マルキンクリーン』なら、24時間365日対応エリアに駆けつけることが可能です。
定期利用でなくまずは1回目のお試し清掃をご希望の場合なども、まずはお気軽にお問い合わせください。
宮城・福島・山形エリア対応
実績豊富なプロが即対応!
水道局指定工事店
24時間365日対応

\事業に悪影響が出る前に/
- グリストラップの清掃に資格は必要ですか?
-
基本的な清掃には必要がありません。ただし、グリストラップ内部にたまった油脂や汚泥(スカム・スラッジ)を取り除いて処分する作業には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
- グリストラップ清掃の流れを教えてください
-
大まかな流れは、以下のとおりです。 1.第1槽(バスケット)のごみを除去する 2.第2槽の汚泥(油脂・沈殿物)を取り出す 3.第3槽(トラップ管)を清掃する
- グリストラップを自分で清掃する場合のリスクはありますか?
-
主に以下のリスクがあります。 ・作業負担が大きい ・衛生状態を悪化させるおそれがある ・清掃業務が店舗責任者に集中しかねない ・健康被害のリスクがある
24時間365日対応! 出張・お見積もり無料! ※深夜帯(22時~5時)は出張費・見積費をいただく場合があります。
今ならWEB限定で3,000円割引中!
0120-365-891