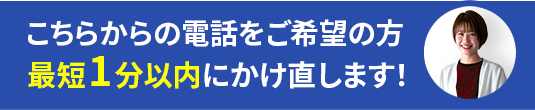貯水槽・受水槽の点検は義務?法定の検査頻度と必須項目まとめ!管理を怠った場合のリスクも解説
この記事では、貯水槽(受水槽)点検の必要性や、法定の頻度、具体的なチェック項目について徹底解説していきます。
給水設備の貯水槽は、利用者の健康に直接影響するため定期的に点検・清掃しなければいけません。点検を怠ると衛生面でトラブルに発展するほか、法律違反による罰則を受けることも。
本記事で紹介している具体的なチェックポイントを参考に、定期点検を実施しましょう。記事後半では頻度やタイミングについても扱っていくので、管理者の方はぜひ参考にしてください。
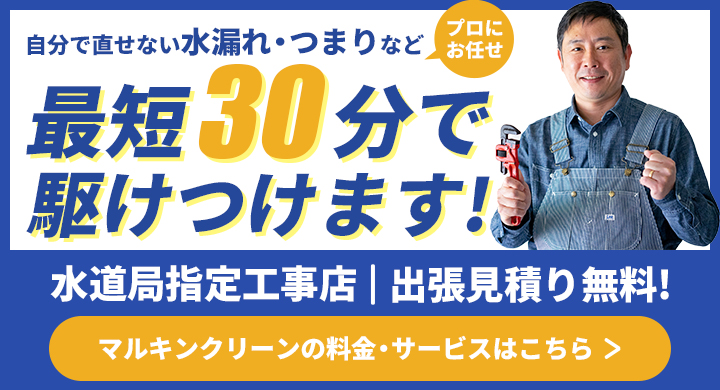
貯水槽・受水槽の点検は法律で義務付け!法定の頻度やチェック項目とは
マンションやオフィスビル、学校、病院などに設置されている受水槽や貯水槽は、安全な水を安定的に供給するため、定期的な点検と検査が欠かせません。点検作業は管理者の努力義務ではなく、水道法やビル管法といった法律で明確に義務付けられています。
ここでは、点検を規定している主な法律と、その内容について詳しく解説します。
水道法
水道法では、有効容量が10㎥を超える受水槽・貯水槽を持つ施設を「簡易専用水道」と定義し、設置者に対して管理義務を課しています。
設置者は厚生労働省令で定められた基準に沿って水道を維持しなければならず、年1回以上は地方自治体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定点検を受ける必要があります。この法令により供給する水が常に安全であることを確認し、異常があれば早急に改善できる体制を整えています。
一方、10㎥以下の小規模水槽は水道法の適用外ですが、多くの自治体で条例により同様の点検が求められるため、規模にかかわらず定期点検は不可欠といえます。
水道法施工規則
水道法施行規則は、水道法で定められた管理義務をより具体的に示したものです。第55条では、以下3点が管理者に義務付けられています。
・水槽の清掃を毎年1回以上実施すること
・有害物質や汚水の侵入を防ぐ措置を講じること
・水の色や臭いなどに異常があれば水質基準に基づいた検査をすること(※引用元:厚生労働省)
また、第56条では簡易専用水道に対する法定点検の頻度を「毎年1回以上」と定めており、点検と清掃の両方を計画的に実施しなければいけません。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)
ビル管法は、多くの人が利用する建物の衛生環境を確保するための法律で、飲料水の安全管理も重要な項目です。
・施行規則第4条:半年ごとに15項目の水質検査を実施
・施行規則第4条第7項:貯水槽の清掃を年1回、残留塩素の検査を7日以内ごとに実施する(※引用元:厚生労働省)
この決まりにより、単発の点検だけでなく日常的な水質監視も義務化。施設管理者は継続的な衛生管理体制の構築が求められます。
ビル管法の対象施設では、法令遵守が安全な水の供給と利用者の信頼維持に直結していると言えるでしょう。
貯水槽・受水槽の点検項目詳細【法定のチェックポイントも】
受水槽や貯水槽の法定点検では、外観や設備の構造だけでなく、内部の衛生状態や水質まで細かく確認します。これらの項目は水道法やビル管法に基づいて定められており、異常があれば改善しなければいけません。
ここでは、法定点検で重視されるチェックポイントを項目ごとに整理しました。
- タンク周囲の状態
- タンク本体の状態
- タンク内部の状態
- タンクマンホールの状態
- 越流管・通気管・水抜管の状態
- 給水管の状態
- 水質検査
具体的なチェックポイントについて見ていきましょう。
タンク周囲の状態
タンク周囲は衛生環境を保つための第一関門です。点検では、作業に支障がないか、周囲が清潔に保たれているか確認します。
- 清掃や修理が支障なく行えるスペースがあるか
- 周囲にゴミや汚物、雑草がないか
- 鳥害や害虫の侵入防止対策がされているか
- 周辺に汚水やたまり水が発生していないか
これらの条件を満たすことで、外部要因による水質汚染を未然に防げます。
タンク本体の状態
本体は水の品質を直接左右する部分であり、構造的な異常がないかを重点的に見ます。
- 亀裂や漏水箇所がないか
- 雨水や汚水が侵入する隙間がないか
- マンホールの位置や形状が点検作業に支障を与えていないか
本体の安全性が確保されていれば、日常的に水質が安定し設備寿命の長期化につながります。
タンク内部の状態
タンク内部は衛生上もっとも重要な箇所であり、汚れや異物混入の有無を確認します。
- 壁面に汚れや付着物がないか
- 浮遊物や濁りが見られないか
- 不要な配管の貫通がないか
- 外壁劣化により光が透過していないか
内部環境の清潔さを保つのは、利用者への安全な水供給に直結します。
タンクマンホールの状態
マンホールは清掃・点検時の出入口であると同時に、外部からの汚染を防ぐ役割も担います。
- 十分な高さの立ち上がりがあるか
- 防水密閉構造で異物侵入を防げるか
- 施錠などで容易に開閉できない構造になっているか
マンホールがしっかり設置してあることで、異物や雨水の侵入を防ぎ、衛生管理を確実にします。
越流管・通気管・水抜管の状態
これらの管は換気や排水の役割をもち、異物や害虫の侵入防止に役立っています。
- 管端部が異物侵入を防ぐ構造になっているか
- 防虫網が破損や目詰まりなく機能しているか
- 排水管との距離が十分に確保され逆流を防げているか
管の安全性確保は、タンク内部の衛生状態を長期間維持するための基本です。
給水管の状態
水源の安全性を確保するため、他の水系統との混合や逆流防止を確認します。
- 他の配管(工業用水や井戸水)と直接接続されていないか
給水管を確認することで、外部からの水質汚染リスクを確実に排除できます。
水質検査
最終的に供給される水の安全性を判断するため、水質検査は必須項目です。
- 臭いに異常がないか
- 味に違和感がないか
- 色に異常(赤・黒・白の変色)がないか
- 濁りがないか
- 残留塩素濃度が0.1mg/L以上あるか
水質検査の結果は貯水槽管理の最終評価であり、利用者の健康を守る重要な証拠となります。
貯水槽・受水槽点検を怠る4大リスク【法律面・衛生面の必要性】
受水槽や貯水槽は、管理を怠ると目に見えない汚染や劣化が進行します。法定点検は法律上の義務であると同時に、利用者の健康と施設の信頼性を守るための重要なプロセスと言えます。
ここでは、点検を怠った場合に起こり得る4つのリスクについて見ていきましょう。
法律違反による罰則を受ける
容量10㎥を超える受水槽や貯水槽は「簡易専用水道」に分類され、水道法に基づき年1回以上の法定点検を受ける義務があります。
怠ると水道法第54条により100万円以下の罰金が科せられる!
罰則の対象は管理会社に限らず、施設の責任者やオーナーにも及ぶため法令遵守は必須です。形式的な点検ではなく、法律で定められた重要な安全管理措置と言えるでしょう。
衛生面でトラブルに発展する
点検しないまま使用を続けると、内部で錆や藻が発生し、虫や異物が混入する危険性があります。これらは水の臭いや色、味の異常を引き起こし、飲用や生活利用に支障を与えるだけでなく、健康被害の原因にもなります。
万が一、利用者が汚染水を口にして体調を崩した場合、賠償請求や信用がなくなるといった深刻な事態を招きかねません。
安全性を損なう
貯水槽本体や付帯設備の劣化は、放置すると水漏れや送水ポンプの故障、断水といった直接的な被害を引き起こします。
高置タンクの場合、亀裂や接合部の隙間から外部の水や汚染物質が侵入するおそれがあり、建物全体の給水の安全性を損ないます。法定点検はこれらの危険を早期に発見し、予防的な修繕につなげる役割を担っています。
貯水槽の劣化が早まる
清掃や検査をしない状態が続くと、内部の汚れや腐食が進み、設備全体の耐用年数が短くなります。錆やコケの付着は槽材を傷め、漏水や構造破損の原因となります。
定期点検は衛生面の維持だけでなく、長期的なコスト削減にもつながる大切なメンテナンスです。
貯水槽・受水槽の点検はどこに頼む?対応業者と費用目安
受水槽や貯水槽の点検や清掃は、法律で定められた資格・登録をもつ業者だけが実施できます。依頼先を選ぶときは、以下2点を確認しましょう。
- 都道府県知事による「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けているか
- 厚生労働大臣の登録をもつ有資格者が在籍しているか
許可のない業者に依頼し点検作業を実施しても、法的には認められません。
また、点検で槽内や周辺設備に劣化や異常が見つかった場合は、清掃だけでなく部品交換や補修などの改善作業に進みます。
貯水槽の耐用年数は一般的に15年程度ですが、保守を怠ればそれより早く性能低下が進みます。定期点検と適切な整備が徹底されていれば、寿命を延ばし安全な水の供給を長期間維持できるでしょう。
貯水槽・受水槽の点検・清掃費用
点検や清掃の費用は、貯水槽・受水槽の容量によって変わります。費用目安は以下を確認してください。
| 貯水槽・受水槽の容量 | 費用目安 |
|---|---|
| 5トン未満 | 2万円〜4万円 |
| 5〜10トン | 3万円〜5万円 |
| 10〜15トン | 4万円〜6万円 |
| 15〜20トン | 5万円〜7万円 |
| 水質検査 | 3,000円〜1万円 |
少しでも点検費用を抑えるなら、複数社から見積もりを取り、価格とサービス内容の両方を比較しましょう。料金だけでなく、法定登録の有無や報告書の発行、改善提案の内容までチェックすることで、安心して任せられる業者を選ぶことができます。
貯水槽・受水槽点検は定期的に!管理は専門業者にお任せを!
本記事では、貯水槽点検の法律関係や必要性、具体的なチェックポイントについて解説しました。頻度やタイミングなどもお分かりいただけたかと思います。
利用者の飲み水や生活に使うための貯水槽は、管理者が定期的に点検依頼しなければいけません。信頼できる業者と定期点検契約などを結ぶと、点検漏れが防げますよ。
マルキンクリーンは、貯水槽点検に対応できる水道修理業者です。点検はもちろん、清掃も承りますので、下記エリアで貯水槽・受水槽を管理されている方は、お気軽にご相談ください!
- 貯水槽の点検はどこに依頼すれば良い?
-
貯水槽や受水槽の点検は、都道府県知事が登録した「建築物飲料水貯水槽清掃業」の業者、または厚生労働大臣の登録を受けた有資格者が在籍する業者に依頼します。許可のない業者は、法的要件を満たさず点検記録として認められません。
- 貯水槽の点検を怠るのは法律違反?
-
有効容量が10㎥を超える貯水槽・受水槽は「簡易専用水道」として扱われ、水道法により年1回以上の法定点検が義務付けられています。怠ると水道法第54条に基づき、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 貯水槽の点検はどれくらいの頻度でする?
-
法定点検の頻度は、容量が10㎥を超える場合であれば年1回以上とされています。清掃や水質検査も含めた総合的な点検であり、衛生状態や設備の劣化を早期発見することが目的です。容量が10㎥以下の小規模貯水槽は水道法の対象外ですが、多くの自治体では条例で同等の点検を求めています。
24時間365日対応! 出張・お見積もり無料! ※深夜帯(22時~5時)は出張費・見積費をいただく場合があります。
今ならWEB限定で3,000円割引中!
0120-365-891